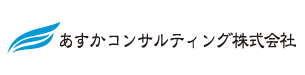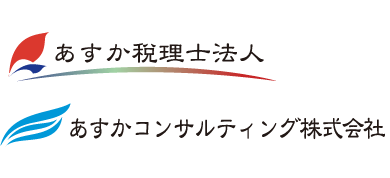BLOGブログ
国際税務2022.07.20 国際税務の基礎①~居住者と非居住者~
海外への移住、企業の海外進出、貿易など海外との繋がりのある個人、企業が増加しています。
海外との取引であっても、日本で課税される場合に判断の基礎となるのは日本の税制です。
日本の税制に基づくので容易に理解ができそうですが、実務上は海外現地の税制が関係してくることや日本の税制における特別な取扱いが複雑に感じさせる要因と考えられます。
今回から数回に分けて、国際税務の基本的な論点を確認していきたいと思います。
1.居住者と非居住者
(1)概要
海外へ移住する人や海外へ出向する人など日本から生活の拠点を海外へ移すが、日本との繋がりが何らかの形で残る方は多いと思います。
そのような方は日本でも税金が課税される可能性が生じますので、まずは「居住者」と「非居住者」の考え方をしっかり理解してください。
日本の税制では「居住者」と「非居住者」で課税範囲が異なります。
そして、「居住者」か「非居住者」を判断する際の「住所」概念について租税法上明文な定義規定が設けられておらず、客観的事実を総合的に判断するものとされています。
このことが自身の状況に当てはめた際に多くの方が悩まれる要因ではないでしょうか。
日本の租税法上の居住者と判断された場合、全世界所得課税とされ、国は課税対象を限定することなく、全面的に課税権を行使することができ 、国内源泉所得のみならず、国外源泉所得に対しても課税対象となります。
一方で、非居住者の場合には、国内源泉所得のみが課税対象となります。
国内源泉所得については次回以降のブログにて解説します。
(2)居住者と非居住者の規定
所得税法5条において納税義務者は、「居住者」と「非居住者」に区分され、「居住者」は、「永住者」と「非永住者」に区分されています。
この意義については、所得税法2条に示されています。
居住者は、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人である(所得税法2条1項3号)。
非永住者は、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人である(所得税法2条1項4号)。
非居住者は、居住者以外の個人である(所得税法2条1項5号)。
このように個人を区分する理由は、その個人の区分に応じ、対象となる課税所得の範囲が異なるためです。
所得税法において居住者の内、永住者に区分された個人は、全ての所得に対して課税権が及び全世界の所得について日本で課税されます(所得税法7条1項1号)。
一方で、居住者の内、非永住者に区分された個人は、国内源泉所得と国内で支払われた若しくは国外から送金された所得に対して課税権が及び(所得税法7条1項2号)、国外所得については日本に送金しない限り日本では課税されないこととなります。
非居住者に区分された個人は、国内源泉所得に対してのみ課税されます(所得税法7条1項3号)
つまり、日本と個人との結びつきの程度に応じ、課税範囲が異なるとお考えください。
「住所」については多くの方が市町村の住民基本台帳に記録されている、いわゆる住民票記載の場所を住所と理解していると思います。
ですが、税法上は「住所」の解釈が明確に定義されているわけではなく、民法22条(※)における住所の意義を借用しているのみです。
※各人の生活の本拠をその者の住所とする(民法22条)。
所得税法における「住所」は民法の概念を借用し「生活の本拠」をいい、「生活の本拠」の判断は客観的事実に基づくとされています(所得税法基本通達2-1)。
生活の本拠とは、ある人が日常生活を送る場合に、主として活動する場所であるとされており、人によっては、仕事の本拠地である場合もあると考えられます。
裁判例においても、所得税法における「住所」の判断要素として、住居・滞在日数、職業活動、生計を一にする配偶者その他の親族の居所、資産の所在等の客観的事実を総合的に判定するとされています。
つまり、所得税法では、個人の判断要素を総合的に判断することで、その個人の生活の中心地がどこであるのかを判定することとされています。

2.米国における個人納税義務者の区分
(1)個人納税義務者
米国において連邦個人所得税の納付義務を負う者は、米国市民(citizens of the United States)と居住者(外国人)の2者に区分されています。
外国人はさらに、居住外国人(resident alien)及び非居住外国人(nonresident alien)の2者に区分されます 。
米国市民とは、米国で生まれた個人、米国外で生まれたとしても両親若しくはどちらかの親が米国市民である個人、米国市民権を取得した個人をいいます 。
居住者(外国人)の定義は、内国歳入法典7701条(b) において示されており、次のいずれかに該当する場合に、居住外国人となります。
居住外国人は、米国での永住権(green card)を与えられた個人 、又は実質的滞在要件 (substantial presence test)を満たす個人をいいます。
非居住外国人は、居住外国人以外の外国人をいいます。
実質的滞在要件は、その年のみではなく、過去2年間の滞在日数も踏まえ形式的な基準により判断することで租税回避の防止を図っています。
具体的には、その暦年中に31日以上米国内に滞在し、かつ、その年の滞在日数、その年の前年の滞在日数の3分の1の日数、その年の前々年の滞在日数の6分の1の滞在日数の合計が183日以上であることが要件となっています。
(2)課税所得の範囲
米国市民は、源泉がどこであるかに関わらず、国内源泉所得及び国外源泉所得のすべての所得が課税対象となります。
米国の課税権が米国市民に対して、広く適用されているのは、市民が海外に居住する場合も、米国市民としての重要な利益を享受するという事実があるためと考えられます。
居住外国人は、米国市民と同様、米国外の源泉を含むすべての源泉から得た所得が課税対象となります。
米国永住者の要件を満たすことで居住外国人となった個人に居住性は、関係がありません。
米国市民及びグリーンカードの要件を満たすことで居住外国人となった個人は、仮に、米国に居住しておらず、海外での活動が実質的には過半を占めている場合であっても、全世界所得に課税されます 。これは、一度市民権あるいは居住権を取得したことによる恩恵に対する代償であるとする見解があります。
米国外で職業活動を行う納税義務者については、内国歳入法典911条に、外国税額控除が規定されています 。
上記の通り、米国市民や外国人居住者は、米国内外問わず全世界所得課税の対象となります。
そのため、911条によりある一定の要件を満たせば、外国に居住する米国市民やグリーンカード保持者の外国人居住者は、総所得から一定の国外稼得所得を控除することができます。
外国に“tax home”を有することとなる一定の要件とは、ボナファイド居住テスト(Bona Fide Resident Test )又は、フィジカル・プレゼンス・テスト(Physical Presence Test)のいずれかを満たすことです。
ボナファイド居住テストとは、真の居住地を判断しようとする基準です。ボナファイド居住テストの要件は、米国市民であり、租税条約締結国に居住していること。さらに、年間を通して外国に居住していること、真の居住者であると長官が納得する形で証明できることです。
フィジカル・プレゼンス・テストの要件は、連続する12ヵ月間の内、外国で330日以上働いていることなどが挙げられます。
330日要件からは、米国外に滞在する日数を重視しているといえます。
(3)日米比較
日本と米国の所得税法上の住所と米国における個人所得税法上の住所について、納税者の区分に応じて課税所得の範囲が異なるのは同様です。
米国においては、国籍基準である点は異なるものの、外国人に関しては、国家と個人の結びつきの強さを個人の住所の所在地により判断していることは、日本と同様です。
日本では上記1の通り、所得税法上住所の意義は、明確に規定されていません。所得税法基本通達2-1により、住所とは生活の本拠であり、生活の本拠は客観的事実により総合的に判断するとされているのみです。
一方で米国は米国における個人所得税法上の居住外国人の居住性の判断方法が、3年間の形式的な基準によって判定していることからすると、個人所得税法上の住所は、現在住んでいる場所を意味するものであると考えられます。
米国の外国税額控除の規定(内国歳入法典911条)において、外国で330日以上働いていることが要件となっていることからも滞在日数を重視していることがわかります。
いかがでしょうか。
日本と米国の居住者の規定を見てきましたが、米国は形式的な要件により日本に比べて居住者の判断根拠が明確に感じます。
日本は課税の判断となる「住所」や「生活の本拠」の判断基準の曖昧さが問題と感じます。
次回はこの曖昧な基準の参考となる、客観的事実に基づいて「住所」を総合的に判断した3つの裁判例を紹介していきます。
あすか税理士法人
【国際税務担当】街 有帆

プロフィールはこちらをご覧下さいませ!