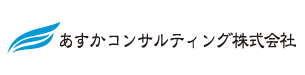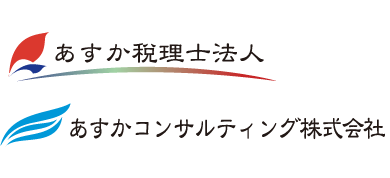BLOGブログ
国内税務2025.10.22 遺産分割がまとまらない!未分割の場合の相続税は?
1.はじめに
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日(通常:被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
そうはいっても、申告期限までに何らかの事情で遺産分割について合意に至らない等、申告期限までに相続財産をどのように分割するかをまとめた遺産分割協議書の作成が間に合わない場合があります。
今回は相続財産が未分割の場合の注意点について、解説いたします。
2.財産未分割の場合の申告方法
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、相続人のうち、一人でも遺産分割協議に参加していない・遺産分割協議書に押印がない場合、その遺産分割協議書は無効とされています。
そのため、先に述べたとおり、相続人間で意見がまとまらない場合は遺産分割協議書の作成は完了しないと言えます。
相続税の申告は、遺産分割がまとまっていない場合であっても、分割されていないということで申告期限が延びることはありません。この場合、相続財産を法定相続分で取得したものとして(包括遺贈の場合には指定の割合に従います)相続税の計算をし、申告と納税を行います。

3.財産未分割の場合の注意点
財産が未分割の場合、その当初申告時には次の相続税の特例を受けることができません。
○配偶者の相続税の軽減(相続税法第19条の2第1項)
○小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4第1項)
○特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の5第1項)
○特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)による改正前の租税特別措置法第69条の5第1項)
これらの特例の適用を受けようとする場合(もしくは受ける可能性がある場合)には、当初申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することで、修正申告又は更正の請求において上記の特例を適用することができます。
なお、その名称の通り、特例の適用ができるのは原則として申告期限から3年以内に分割があった場合に限られます。
更正の請求を行う場合は、分割が行われた日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求を行うことが必要です。
ただし、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において相続をめぐって裁判になっているなど、一定のやむを得ない事情がある場合には、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を所轄税務署長宛てに提出し、その承認を受け、判決の確定の日など相続財産の分割ができることとなった日の翌日から4か月以内に分割されたときは、これらの特例の適用を受けることができます。
また、次の特例等については、租税特別措置法において相続税の申告書の提出期限までに遺産分割がなされている事が要件である旨の明記があり、後に遺産分割が確定したとしても適用することが出来ません。
○農地等についての相続税の納税猶予及び免除等
○山林についての相続税の納税猶予及び免除
○特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除
○個人事業者の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除
○非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除
○医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除
もう一点、相続財産が未分割の場合には相続財産の所有権の帰属が確定していない状況にあるため、物納(相続した財産そのものを税として納める)が認められないことにも注意が必要です。
4.まとめ
上記をまとめると次の点に注意をして準備を進める必要があります。
①未分割でも申告期限内に申告かつ必要に応じて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出
②納税資金の確保
あとから還付を受けられる可能性はあっても当初申告では上記で取り上げた特例を適用することができないため、当初申告で多額の納税となる可能性があります。
相続税は相続により取得した財産額を限度として連帯納付義務があるため、まずは相続人同士で当初申告による相続税額を納める資金が必要です。
③遺産分割協議を申告期限から3年以内にまとめる
④仮に裁判等で遺産分割協議がまとまらない場合には申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出
⑤遺産分割協議が成立した日(承認申請書を提出している場合には判決の確定日等、分割ができることとなった日)の翌日から4ヶ月以内に更正の請求を行う
余談ですが、相続税法基本通達第17条では、相続税の按分割合における端数処理について定められています。
複数の相続人が共同で取得した財産の相続税額を計算する場合に、小数点以下2位未満の端数をどのように扱うかを規定したもので、「その財産の取得者全員が選択した方法により、各取得者の割合の合計値が1になるようその端数を調整して、各取得者の相続税額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする」とされています。
国税庁が公表している令和7年度の相続税の申告書の様式を確認すると、按分割合は小数点以下10桁まで記載可能であることが分かります。
例えば、法定相続人が子の相続人3名のみで、法定相続分で各人の相続税額を算出するとした場合、相続人3名全員の同意により0.3333333333/0.3333333333/0.3333333334という按分割合で申告が可能です。
当初申告でひとまず納付という状況下で、できるだけ納付額に不公平がないようにする場合の参考になれば幸いです。
あすか税理士法人
【スタッフ】中村麻侑子