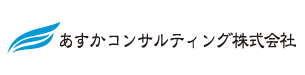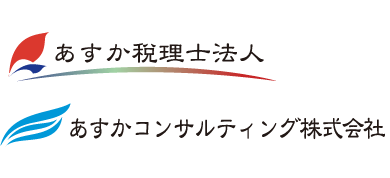BLOGブログ
会計・ファイナンス・監査2025.11.12 新しいリース会計基準について(4)
既にご承知の方も多いと思いますが、2024年9月、企業会計基準委員会(ASBJ)は、「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号、以下「基準」)及び「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号、以下「適用指針」)を公表しました。今回は、新しいリース会計基準の適用に伴う実務上の論点について確認したいと思います。
※新しいリース基準の概要については、こちらもご覧ください。
1.借地権の設定に係る権利金等
借地権とは、借地法及び借地借家法において定められた「建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権」のことを指します。土地の賃貸借契約の締結時に借地権の設定対価として権利金の授受が行われることがあると思いますが、会計基準では、その授受される金銭の性質はさまざまであるとされています。
そこで、適用指針においては、以下のものを想定して、会計処理が定められています。
・借手が貸手と借地契約を締結するにあたり、貸手に対して支払う借地権の設定対価
・借手が貸手と借地契約を締結するにあたり、貸手が借手以外の第三者と借地契約を締結していた場合に借手が第三者から借地権の譲渡を受けるときの第三者に対する借地権の譲渡対価
借地権の設定に係る権利金等の授受が行われる場合、借地権を除く底地に対して毎月支払う賃料が設定され、借地権の価格の土地の更地価格に対する割合が高い場合には当該賃料は低くなるという一定の関係性があるとされています。
(1)借手の原則的な会計処理
借地権の設定に係る権利金等は、使用権資産の取得価額に含め、借手のリース期間を耐用年数とし、減価償却を行うこととされています【適用指針.27】。
この処理は、借地権が土地を使用する権利に他ならず、土地の賃貸借においては借手が土地を賃借しながら借地権のみを第三者に譲渡することはできないと考えられること、また、通常当該権利金等の支払は土地の賃貸借契約と同時又はほぼ同時に行われることを踏まえて、借地権の設定と土地の賃貸借とを一体として取り扱うべきものという考え方に基づいています。
(2)借手の例外的な会計処理
旧借地権や普通借地権の設定に係る権利金等のうち、次の①または②に該当するものについては、減価償却を行わないことが認められています【適用指針.27但書】。
① 新しい基準の適用前に当該権利金等を償却していなかった場合
・適用初年度の期首に計上されている当該権利金等
・適用後に新たに計上される普通借地権の設定に関する権利金
② 新しい基準の適用初年度の期首に当該権利金等が計上されていない場合
・適用後に新たに計上される普通借地権の設定に係る権利金等
ここで、旧借地権とは借地法の規定により設定された借地権のことを指し、普通借地権とは定期借地権以外の借地権で旧借地権を除いたもののことを指します。
旧借地権または普通借地権については、以下の2つの見方が存在するとされています。
①法定更新制度や正当事由制度により、借手の権利が強く保護されており、借地権の設定対価は、減価しない土地の一部取得に準ずるとの見方
②契約で期間を定めている場合には、契約期間(契約で期間を定めていない場合には法定存続期間)がある上で、契約の更新の権利があるものであると考えられ、通常、借地権は無期限ではないと考えられるため、借地権の設定対価も賃借期間に要するコストであるとの見方
適用指針では、このような点を踏まえ、借地権は土地を使用する権利に他ならず土地の賃貸借においては借手が土地を賃借しながら借地権のみを第三者に譲渡することはできないという一定の関係性があるという前提において、借地権の設定対価も賃借期間に要するコストであるとの見方に基づき、旧借地権や普通借地権についても、原則的な処理は変わらないものとされています。
一方で、我が国の取引慣行においては、上記①の考え方を支持する意見があることを踏まえ、例外的な処理が認められています【適用指針.BC55】。なお、このような権利金等を別個のものとして取り扱うことは適切ではないと考えられるため、減価償却を行わない場合においても、当該権利金等の表示については、基準.49に従って表示することに留意が必要です【適用指針.BC55】。
また、定期借地権が設定される土地の賃貸借契約は、賃借期間の満了時に当該賃貸借契約が終了するため、定期借地権の設定に係る権利金等は、原則的な会計処理を行うこととなります【適用指針.BC57】。
2.建設協力金等の差入預託保証金
(1)敷金を除く建設協力金等の会計処理
敷金を除く建設協力金等については、以下の会計処理を行うこととされています【適用指針.29】。
・貸手(預り企業)から、借手(差入企業)に将来返還される建設協力金等の差入預託保証金に係る当初認識時の時価は、返済期日までのキャッシュ・フローの割引現在価値となる
・借手(差入企業)は、差入保証金の支払額と時価との差額を使用権資産の取得価額に含める
・当該時価と返済額との差額は、弁済期または償還期に至るまで毎期一定の方法で受取利息として計上する
建設協力金は、建物建設時に消費寄託する建物等の賃貸に係る預託保証金であり、契約に定めた期日に預り企業(貸手)が現金を返還し、差入企業(借手)がこれを受け取る契約であるため、金融商品に該当します。
金融商品会計実務指針においては、敷金を除く将来返還される建設協力金等の差入預託保証金について、
・建設協力金は、建物等の賃貸に係る預託保証金であり、金利が付かない期間または低金利の期間、賃借人にとって機会金利を賃料として計上する方法が考えられる
・建設協力金等が、流動化の目的で売却されたときに現在価値で計上していない矛盾が売却損という形で顕在化する
・一方で、建設協力金等は、売却しなければ寄託債権という金銭債権であり、取得価額で計上され時価評価されないから、当初認識は取得価額で十分との考え方もある
・売却した場合としない場合で整合性のある処理を定めるべきである
との整理を行った上で、以下の会計処理を定めています。
・当初認識時の時価は、返済期日までのキャッシュ・フローを割り引いた現在価値が建設協力金等の時価である
・支払額と当該時価との差額は、長期前払家賃として計上し、契約期間にわたって各期の純損益に合理的に配分する
・当初時価と返済金額との差額を契約期間にわたって配分し受取利息として計上する
・差入預託保証金のうち、将来返還されない額は、賃借予定期間にわたり定額法により償却する
リース会計基準においては、借手のリース料の定義(借手が借手のリース期間中に原資産を使用する権利に関して行う貸手に対する支払)を踏まえ、金融商品会計実務指針において長期前払家賃として取り扱われていたものについて、利息の受取を低額とすることによる賃料の支払の性質を有すると考えられるため、リース料として使用権資産の取得価額に含めることとされています。
また、敷金を除く差入預託保証金のうち、預り企業(貸手)から差入企業(借手)に将来返還されないことが契約上定められている金額は、借手が賃貸借契約に基づいて原資産を使用する権利に関する支払である点で、毎月支払われるリース料と相違はないと考えられるため、こちらも使用権資産の取得価額に含めることとされています。
建設協力金に関して、差入企業(借手)が対象となった土地建物に抵当権を設定している場合、割引現在価値を算出するための利子率は、原則としてリスク・フリーの利子率を使用することとなっています【適用指針.30】。
また、差入企業(借手)は、その影響額に重要性がない将来返還される建設協力金(例.返済期日までの期間が短いもの等)については、原則的な会計処理(適用指針.29)の会計処理を行わないことができ、この場合は債権に準じて会計処理を行うとなります【適用指針.31】。
差入企業(借手)は、預り企業(貸手)から将来返還されないことが契約上定められている差入預託保証金については、使用権資産の取得価額に含める必要があります【適用指針.32】。
(2)敷金の会計処理
差入企業(借手)が差し入れた敷金については、以下の取扱いとなっています【適用指針.33及び34】。
・預り企業(貸手)から将来返還される部分
→取得原価で計上するが、適用指針.29及び30(敷金を除く建設協力金等)に準じて会計処理を行うことができる
・預り企業(貸手)から返還されないことが契約上定められている部分
→使用権資産の取得価額に含める
敷金は、賃料及び修繕の担保的性格を有し、償還期限は賃貸借契約満了時であり、法的には契約期間満了時に返還請求権が発生すると解されており、通常無金利であることから、建設協力金と異なり取得原価で計上することとしていた金融商品実務指針の取扱いが踏襲されています。一方で、IFRS 任意適用企業が IFRS 第 16 号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となる会計基準の開発を行う方針を考慮し、差入敷金について建設協力金と同様の会計処理も認めることとされています【適用指針.BC64】。
一方、差入敷金のうち、預り企業(貸手)から差入企業(借手)に将来返還されないことが契約上定められている金額については、リースの借手が賃貸借契約に基づいて原資産を使用する権利に関する支払である点で、毎月支払われるリース料と相違はないと考えられるため、当該金額を使用権資産の取得価額に含めることとされています【適用指針.BC65】。
(3)貸倒引当金の計上
建設協力金等の差入預託保証金について貸手(預り企業)の支払能力から回収不能と見込まれる金額がある場合、金融商品会計基準に従って貸倒引当金を設定する必要があります【適用指針.36】。
(次回につづく)
あすかコンサルティング株式会社
【会計コンサルティング担当】津田 佳典
プロフィールはこちらをご覧くださいませ!