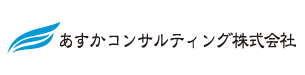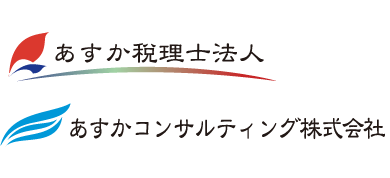BLOGブログ
国内税務2025.07.23 重加算税の適用可否~仮装又は隠蔽とは?~
1.はじめに
前回のブログでは、4つの加算税について取り上げました。
そのうち最も重いペナルティを課されるのが重加算税です。
国税庁は重加算税の適用について、「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」を公表しています。
これは法人税の重加算税の賦課に関する取扱基準の整備等を図る趣旨で、国税通則法第68条第1項若しくは第2項又は第4項の規定の適用に関し留意すべき事項等を定めたものです。
つまり、税務調査での国側の視点(判断基準)と捉えるのが良いでしょう。
まずはこの事務運営指針の内容を簡単に確認したうえで、裁決事例を取り上げ、最後に私見を述べたいと思います。
2.法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
事務運営指針は、「第一 賦課基準」「第二 重加算税の取扱い」「第三 重加算税の計算」「第四 通算法人等に係る取扱いの適用」という構成になっています。
第一の賦課基準は次の項目に分かれています。
◯ 隠蔽又は仮装に該当する場合
◯ 使途不明金及び使途秘匿金の取扱い
◯ 帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない場合
◯ 不正に繰戻し還付を受けた場合の取扱い
◯ 隠蔽仮装に基づく欠損金額の繰越しに係る重加算税の課税年度
◯ 隠蔽仮装に基づく最後事業年度の欠損金相当額の損金算入に係る重加算税の課税年度
さらにこの中で重加算税の対象になるかどうかという判断において重要となるのが一つ目から三つ目の項目であり、取りまとめると下記の通りです。
*隠蔽又は仮装とは「不正事実」がある場合をいう
⇒「不正事実」の例
・二重帳簿の作成
・帳簿書類の隠匿、虚偽記載等
①帳簿書類の破棄又は隠匿
②帳簿書類の改ざん、虚偽記載、相手方との通謀による証憑の作成等の仮装経理
③帳簿書類へ記録せず、売上等収入の脱ろう又は棚卸資産の除外
・特定の損金算入又は税額控除の要件とされる証明書の改ざん等
・簿外資産に係る収入の未計上
・簿外資金による役員賞与等の支出
*使途不明金について次の事実がある場合には「不正事実」に該当する
・帳簿書類の破棄、隠匿、改ざん等があること
・取引の慣行、取引の形態等から勘案して通常計上すべき勘定科目に計上されていないこと
*次の場合には帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない(相手方との通謀又は証憑書類等の破棄・破棄・改ざんでない事が前提)
・売上等の収入の計上の繰延で、その売上等が翌事業年度の収益に計上されている場合(いわゆる期ズレ)
・経費の繰上計上で、その経費が翌事業年度に支出されたことが確認できる場合(上記同様期ズレ)
・棚卸資産の評価替えにより過小評価をしている場合
・交際費や寄付金等、損金算入について制限のある費用を単に他の費用科目に計上している場合
上記に照らすと、税務調査では「不正事実」の例に該当する場合に重加算税を課す可能性があると予測することができます。
3.裁決事例の紹介
事務運営指針は先に述べたとおりですが、次に、仮装と隠蔽(不正事実)について国側の判断と納税者の主張が対立した裁決事例を取り上げます。
《令和5年2月8日裁決》https://www.kfs.go.jp/service/JP/130/02/index.html
【事案の概要】
本件は、審査請求人(以下「請求人」という。)が、原処分庁所属の職員の調査を受けて、法人税等及び消費税等の修正申告をしたところ、原処分庁が、請求人の売上げの計上漏れについては、隠蔽又は仮装の事実が認められるとして法人税及び消費税等に係る重加算税の賦課決定処分を行ったのに対し、請求人が、隠蔽又は仮装に該当する事実はないなどとして、原処分の全部の取消しを求めた事案である。
【争点】(争点2を抜粋)
請求人に通則法第68条第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があるか否か。
【審判所の判断】
通則法第68条第1項に規定する「隠蔽し」とは、課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実について、これを隠匿あるいは故意に脱漏することをいい、「仮装し」とは、所得、財産、あるいは取引上の名義等に関し、あたかもそれが真実であるかのように装うなど、故意に事実をわい曲することをいうものと解される。
⇒請求人が課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実について、隠匿あるいは故意に脱漏したとまでは認められないことから、本件工事代金が請求人の申告漏れとなったことは、通則法第68条第1項に規定する「隠蔽」に該当するとは認められず、通則法第68条第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認めることはできない。
↓具体的には・・・
・過失により本件工事代金について領収証の発行を行わなかった事実が認められるだけで、同人が、故意に本件工事代金に係る領収証を発行しなかった事実まで認められるものではない。
・工事代金についてのみ領収証の作成や帳簿への記載がなされなかったことが意図的なものであるとうかがい得るような規則性・共通性なども見いだし難い。
・請求人が、本件工事代金について、故意に領収証を発行しなかったこと、あるいは、領収証を作成しながらその控えを故意に破棄したことなどにより、故意に帳簿に記載しなかったことを裏付ける証拠は見当たらない。
《平成31年3月1日裁決》https://www.kfs.go.jp/service/JP/114/02/index.html
【事案の概要】
本件は、生コン製造販売業を営む審査請求人(以下「請求人」という。)の法人税等について、原処分庁が、実際の取引がないにもかかわらず恣意的な金額を各事業年度の材料仕入れとしたことは、隠ぺい又は仮装の行為に該当するなどとして更正処分等を行ったのに対し、請求人が、当該会計処理は、過去の事業年度における仮装経理に基づく過大申告を是正する目的で行った修正の経理であり、隠ぺい又は仮装に該当する事実はないなどとして、原処分の一部の取消しを求めた事案である。
【争点】(争点4を抜粋)
請求人に、平成28年改正前通則法第68条第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」に該当する事実があったか否か。
【審判所の判断】
事実を隠ぺいしたとは、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいしあるいは故意に脱漏したことをいい、また、事実を仮装したとは、所得、財産あるいは取引上の名義等に関し、あたかも、それが真実であるかのように装うなど、故意に事実をわい曲したことをいうと解される。
⇒J社からの材料仕入高につき、実際とは異なる水増しした材料仕入高を帳簿書類に計上したことは、行為の意味を理解しながら故意に事実をわい曲したものということができ、請求人において、J社からの材料仕入高につき、水増し後の材料仕入高であるかのように仮装したものというべきである。平成28年改正前通則法第68条第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。
↓具体的には・・・
・本件代表者は、経理担当者からの決算利益にあまり影響が生じないような金額で複数の事業年度に分けて材料仕入高として経費を計上したい旨の相談に対し、一度に多額の材料仕入高を計上した場合には金融機関から借入金の返済要求がされるなどの影響が生じると考え、複数の事業年度に分けて計上することを了承した。
・本件代表者による当該了承を受け、経理担当者は、本件各事業年度において、実際には取引等の事実がないJ社からの材料仕入高を計上する会計処理を行ったことが認められるから、本件各事業年度におけるJ社からの材料仕入高につき実際とは異なるものであることを認識しながら、水増しした材料仕入高を帳簿書類に計上していたものと認められる。
《平15.2.20裁決》https://www.kfs.go.jp/service/JP/65/05/index.html
【事案の概要・争点】
本件は、美容業を営む同族会社である審査請求人(以下「請求人」という。)が受領した紹介手数料等を代表者の個人名義の預金口座に入金することなどにより、その一部を益金の額に算入しなかったことについて、国税通則法(以下「通則法」という。)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項の規定を適用して更正処分をすることができるか否かを主な争点とする事案である。
【審判所の判断】
加算税の一種である重加算税は、脱税者の不正行為の反社会性又は反道徳性に対して科される刑事罰とは異なり、納税義務違反が事実の隠ぺい又は仮装という不正な方法に基づいて行われたと判断された場合に違反者に対して特に重い経済的負担を課すための行政上の措置であるといえる。
このような制度の趣旨にかんがみれば、重加算税を課すためには、課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部の隠ぺい又は仮装があり、その隠ぺい又は仮装の行為を原因として過少申告の結果が発生したものであれば足り、それ以上に、申告に際し、納税者において過少申告を行うことの認識を有していることまで必要とするものではないと解すべきである。
そして、ここにいう事実を隠ぺいするとは、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実について、これを隠ぺいし又は脱漏することをいい、事実を仮装するとは、所得、財産又は取引上の名義等に関しあたかもそれが事実であるかのように装う等事実をわい曲することをいうものと解される。
⇒通則法第68条第1項の規定に基づき、隠ぺいの事実に係る部分の税額を計算の基礎としてなされた本件法人税賦課決定処分は適法である。
↓具体的には・・・
・請求人は、本件紹介手数料を本件公表外銀行預金口座に振り込ませていたほか、本件仕入割戻金を現金で受領するなどして、いずれも本件公表帳簿に記載せず隠ぺいし、これに基づいて申告したことが認められる。このような請求人の行為は、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、隠ぺいしたところに基づき納税申告書を提出していたときに該当する。
上記の裁決を参考にすると、実務上次の様な点が重加算税適用可否の判断基準になるかと思います。
○隠蔽とは、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠す、故意に漏らすこと。
○仮装とは、所得、財産、あるいは取引上の名義等について、故意に事実をわい曲すること。
○故意かどうかを裏付ける証拠、事実が認められると重加算税を課される可能性が高い。
○重加算税の賦課要件は隠蔽や仮装の事実であり、過少申告の認識まで必要とはされていない。

4.まとめ(私見)
前回のブログで条文を確認しましたが、重加算税は「課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装」があることが賦課要件です。
そして、裁決事例でも述べられていることからも分かるように「隠蔽」や「仮装」の事実は、納税者側の「故意」無しには発生し得ないと考えています。
(勿論、「故意」については、納税者の主観のみで判断されるものではなく客観的に見て「故意」ではないと推定される背景が必要です。)
ただ、税務調査ではあくまで事務運営指針に基づいた視点から帳簿(=「課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実が反映されていない」という結果)を確認し、重加算税の判断がされている様に見受けられます。
重加算税が賦課されるとそもそも該当する事業年度におけるペナルティの額が非常に大きいという点はありますが、青色申告承認取消しの恐れや、税務調査の頻度が高くなる可能性もあり、その影響は計り知れません。
税務調査で重加算税の対象だと指摘を受けた後、税務署は質問応答記録書を作成し、納税者がサインをすることで重加算税の賦課決定がなされます。
意図せずそのような指摘を受けた場合には、調査対応が長引く可能性はありますが将来的な影響を鑑み、安易に質問応答記録書にサインするのではなく、重加算税の指摘を受けるに至った経緯を詳細に整理し、隠蔽や仮装の事実はないこと、故意ではなく生じてしまったということをきちんと主張することが大切だと考えます。
あすか税理士法人
【スタッフ】中村麻侑子