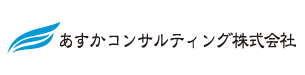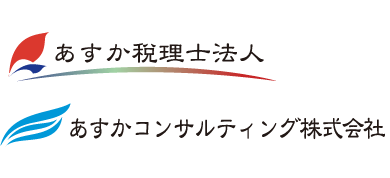BLOGブログ
国内税務2025.04.30 棚卸資産の評価方法~変更手続きについて~
1.はじめに
前回のブログでは、棚卸資産の評価方法について確認しました。
今回は、自社の評価方法を見直した結果、他の評価方法を採用した方が良いと考えられる場合にとるべき手続きについて解説いたします。
2.手続きの概要
(1)手続名
棚卸資産の評価方法・短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出方法・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更承認申請書
(2)提出期限
変更しようとする事業年度開始の日の前日まで
手続名にもあるように、棚卸資産だけではなく短期売買商品や有価証券等の帳簿価額の算出方法についても同様の申請書を用います。
なお、例えば棚卸資産の評価方法と有価証券の算出方法を同時に変更する場合には、別々に申請書を提出する必要がありますのでご留意下さい。
また、当該手続きは提出すれば完了するものではなく、納税地の所轄税務署長の承認を受けることが必要です。
一旦採用した棚卸資産の評価方法は継続適用が原則で、みだりに変更することは認められておらず、現在の評価方法を採用してから相当期間経過していないときや、所得計算が適正に行われないような評価方法の場合には、税務署長は変更承認申請を却下することができます。
なお、ここでの「相当期間」は「3年」とされています。(法人税基本通達5-2-13)
ただし、3年経過したからといって特段の理由なく無条件にその変更申請が認められる訳ではありませんのでご留意下さい。
また、法人が合併したことに伴って被合併法人と合併法人の評価方法とを斉一のものに合わせるなど、変更することに合理的な理由がある場合には3年経過前であっても承認されるものとされています。
変更しようとする事業年度開始の前日までに申請書を提出し、変更しようとする事業年度終了の日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、その事業年度終了の日において承認があったものとみなします。

3.手続きの内容
当該手続きは、事業の種類ごと&資産の区分ごとにそれぞれ異なる評価方法を選定することができます。
資産の区分とは次の5区分をいいます。(法人税法施行令第29条第1項)
①商品又は製品
②半製品
③仕掛品
④主要原材料
⑤補助原材料その他の棚卸資産
さらに、細かく細分することで棚卸資産の評価額をより適正に計算できる場合には事業所別又は上記の5区分を更に合理的な区分毎に細分した異なる方法を選定することもできます。(法人税法基本通達5-2-12)
例)
事業の種類:繊維製品卸売業
資産の区分:商品
高級輸入品と国産規格品を取り扱っており、品質、価格、仕入経路等が著しく異なる
→輸入品と国産規格品に区分してそれぞれの評価方法を選定することができる
また、5区分のうち同一区分に属する棚卸資産については原則同一の評価方法によるべきとされていますが、同一区分の中に個別法を選定することができるものがある場合(前回ブログ参照)に、その区分の全部について同一方法の選定を強制することは妥当ではないと考えられています。
個別法を選定することができるものについては、同一区分の他の棚卸資産と区分して個別法を選定をすることができるとされています。(法人税法基本通達5-2-12)
上記の例で、高級輸入品のみ個別管理を行っているような場合には、同じ商品であっても高級輸入品のみ個別法の採用が認められるというイメージです。
4.まとめ
いかがでしょうか。
棚卸資産の評価額(在庫額)というのは会社の損益に直接影響があるので安易な変更は勿論認められません。
そのため、各評価方法を理解した上で、自社の棚卸資産を適正な評価額にするためには何が適しているのか?という視点で考えることが大切です。
区分毎に選定できるというのがポイントで、例えば、為替や物価の変動が非常に大きいにもかかわらずすべての在庫を最終仕入原価法で評価している場合には、少しでもその影響を平準化させるために影響を受けやすい主要部品については総平均法を採用する、といったことが考えられます。
適切な在庫管理は、会社の利益予測・キャッシュフローを考える場合にも非常に重要な点ですので、時間をかけて検討するのが望ましいと考えます。
あすか税理士法人
【スタッフ】中村麻侑子