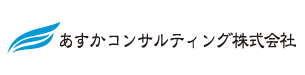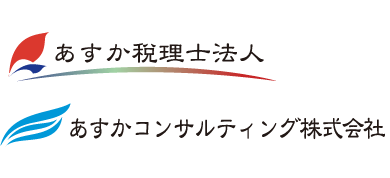BLOGブログ
国内税務2025.05.28 分掌変更等の役員退職金の取扱い
1.はじめに
役員退職給与は、役員を辞任(退職)する際に支給されるのが一般的です。
しかし、引き続き役員に在職する場合でも、実質的には退職したと認められ、
その役員に対して支給した給与も法人税法上の退職給与として認められる場合があります。
今回は、その取扱いについて確認していきたいと思います。
2.法人税法基本通達9-2-32
まずは、役員が分掌変更した場合の退職金の取扱いが規定されている通達の内容を見ていきましょう。
《役員の分掌変更等の場合の退職給与》
9-2-32 法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。
(1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。
(2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。)になったこと。
(3) 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。
(注) 本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。
このように、法人税法基本通達9-2-32では、役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情と認められる場合を、例示として3つ挙げています。しかし、この3つの例示に該当したからといって、本通達の適用が認められるわけではない点に注意が必要です。
あくまで例示に過ぎず、例示された形式的な側面のみで判断をするのではなく、実質的側面から判断をすることが必要となります。
3.具体的な考え方・留意点
・実質的判断
上記でも述べましたが、本通達は、あくまで実質的な現役経営者からの引退を前提としているため、単に、常勤役員が非常勤役員になった、監査役になった、給与が50%以上激減したなどの、単なる肩書きの変更で業務内容に変化がない場合には、退職したと同様な事情とは捉え難いのが実情です。
・経営上主要な地位の判断
経営上主要な地位とはどういうことなのか。
明確な規定はありませんが、判例で挙げられている例示を参考にすると次のような状態であると考えることができます。
①筆頭株主であること
②重要な取引先である金融機関との交渉
③取締役会等に出席し、決議に参加していること
④従業員に指示を与えていること
⑤重要な事業用資産のの売却取引等の設備投資に対する最終意思決定を行っていること
⑥同業者団体の行事にその会社の代表者として継続的に参加している事実
⑦事業活動に広く関与していること
⑧従業員の採用決定や給料等の査定
このような事実を総合的に判断した上で、経営上主要な地位を占めていると判断されます。
・損金算入時期
通常、退職した役員に対する退職給与の損金算入時期は、「株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度」と「退職給与の額を支払った日の属する事業年度」のどちらかから選択することができるとされています。
しかし、本通達9-2-32の分掌変更による役員退職金は、原則として、未払計上が認められていないため、注意が必要です。

4.まとめ
分掌変更による役員退職給与は、通達で上記のような取り扱いをしていますが、あくまで例示に過ぎず、その結果納税者側と課税庁側で多くの争いが生じているのも事実です。そのため、法律で明記すべき取扱いだと改めて感じるところではありますが、本通達を適用して役員退職給与を支給する場合には、職務の内容や地位の変更が実質的に退職したと同様の事情にあたるのか否か、実態を総合的に判断する必要があります。そのため、経営に従事していないということが証明できる対応は重要となってくるといえるでしょう。
あすか税理士法人
【スタッフ】渋谷優果