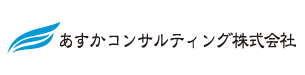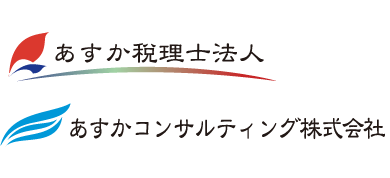BLOGブログ
国内税務2025.10.08 令和7年度の年末調整何が変わる・・・?
今年もあっという間に年末調整の時期が近づいてきました。
令和7年度の年末調整からいろいろ変わると耳にすることも多いかもしれませんが、
実際のところ何が変わるのか、改正の背景も踏まえ内容を確認していきたいと思います!
1.令和7年度の年末調整の改正ポイント
まずは、変わるポイントは次の4つになります。
①基礎控除の引き上げ
所得税の基礎控除は、定額であることから、物価が上昇すると実質的には税負担が増えてしまいます。消費者物価指数は、最後に基礎控除の引き上げが行われた平成7年から令和5年にかけて10%程度上昇、令和6年も10月までに3%程度上昇しているとされています。
そこで、近頃の物価高騰により今後も一定の上昇が見込まれることから、物価動向を勘案し、基礎控除が引き上げられます。
②給与所得控除の引き上げ
給与所得控除は、給与収入額に応じてそれぞれの割合に基づき、控除額が計算されます。給与収入が上昇すれば物価上昇とともに控除額も増加する仕組みとなっています。
しかし、例えばパートやアルバイトの方などある程度の給与水準に抑えて働く方など、最低保障額が適用される収入である場合には、収入が増えたとしても控除額は増加しない構造となっていました。そういった方の税負担を軽減するために、就業調整にも対応し、給与所得控除の最低保障額が引き上げられます。
.png)
(財務省より)
③特定扶養控除の見直し・特定親族特別控除の創設
改正の中で一番この改正が混乱するかもしれません。
この改正は、大学生年代の子(19歳以上23歳未満の方)を持つ親向けの改正です。
近年の厳しい人手不足の中、特に大学生世代がアルバイトをする際に「親の扶養から外れてしまうから」といった税制が一因となり就業調整をするケースが多く見られました。そういった働く時間を制限する事態を解消するため、特定扶養親族の所得要件を引き上げ、同時に、特定扶養親族の所得要件を超えた場合でも、控除額を段階的に逓減するといった特定親族特別控除が創設されました。
④扶養親族等の所得要件の引き上げ
基礎控除の引き上げ改正に伴い、扶養親族や同一生計配偶者の所得の要件が引き上げられました。
それでは、具体的な改正の内容を見ていきましょう。
2.基礎控除の引き上げ
.png)
(国税庁より)
改正前は、合計所得金額が2,350万円以下であれば、一律48万円でしたが、
改正により、基礎控除額58万円となり、48万円から10万円引き上げられました。
令和7・8年分については、合計所得金額が655万円以下の場合には、基礎控除額58万円に所得階層ごとに4段階(37万円、30万円、10万円、5万円)で上乗せした金額となっています。
低~中所得層の税負担に配慮した改正ですね。
※日本国内に住所等がない非居住者でも、基礎控除の適用はありますが、この4段階加算は居住者についてのみ適用されます。
※合計所得金額が2,350万円超の方には、基礎控除の改正の影響はありません。
3.給与所得控除の引き上げ
.png)
(国税庁より)
給与所得控除は、最低保障額が55万円⇒65万円に引き上げられました。
※給与収入が190万円超の方にには、給与所得控除の改正の影響はありません。
4.特定扶養控除の見直し・特定親族特別控除の創設
まず、従来の「特定扶養控除」は、扶養親族が19歳以上23歳未満で、合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)である場合に、一律63万円の控除を受けることができていました。
しかし、この場合、特定扶養親族の収入が、103万円を1円でも超えてしまうと、控除額が段階的に減額されるのではなく、控除が一切受けられなくなっていました。103万円だと控除63万円で、104万円だと控除0はなかなか残酷ですよね・・・
★所得金額要件が48万円(給与収入103万円)以下⇒58万円(給与収入123万円)へ引き上げ
★58万円(給与収入123万円)を超えた場合にも段階的な特別控除の創設
★特定親族特別控除の適用を受けるためには、新しく「特別親族特別控除申告書」という欄が「基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除」が兼用されている申告書に追加されているので、記入漏れがないように気をつけましょう。
.png)
.png)
(国税庁より)
5.扶養親族等の所得要件の引き上げ
扶養親族・同一生計配偶者の所得要件が、48万円⇒58万円に引き上げられました。
.png)
(国税庁より)
いかがでしたでしょうか。
改正に至った背景も踏まえ、まとめてみました。
年末調整の申告書を記入する際には、説明をよく読んで漏れがないよう記入するよう心がけてください。
あすか税理士法人
【スタッフ】渋谷優果