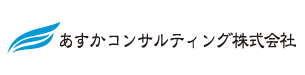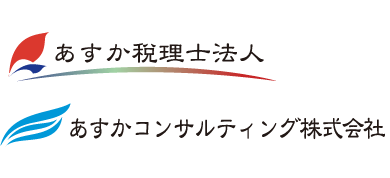BLOGブログ
国際税務2025.08.27 輸出免税に係る注意点
今回は輸出免税の誤りやすい事例について、ポイントを絞り整理していきたいと思います。
1.輸出許可書の名義人が異なる場合
輸出免税は、税関に輸出申告をして、輸出許可書が交付された輸出者本人に適用されます。
一般的には、財務大臣の許可を受けている通関業者が輸出入者本人の名義で通関手続きを代理します。この場合、輸出申告書の輸出者は、通関業者ではなく輸出者本人となりますので、輸出者本人が輸出免税を受けることができます。
実務上、商社等が仲介となり、代わりに輸出申告手続きを行うこともあります。この場合、輸出申告書の輸出者は、商社となります。このままでは、商社が輸出免税適用者となり、実際の輸出者に輸出免税の適用がありません。
そのため、実際の輸出者が、輸出免税の適用を受けるためにすべきことは、次のとおりです。
①輸出許可書の原本を入手し、保存
②『消費税輸出免税不適用連絡一覧表』を交付し、商社等に輸出免税の適用がない旨を連絡
→該当する取引の金額等を記載し、記載した取引についての輸出免税適用者は当社ですよといった旨を名義貸しに係る事業者(商社等)に連絡するものです。
③税法上、今回の取引は、商社等の売上・仕入として認識されないことを指導
2.国内自社工場を経由して、輸出した場合
貿易取引では、インコタームズにより、貿易から生じる費用や危険リスクの売主と買主間での負担範囲を取り決めています。よく使われるものに、FOB、CIF、EXWがありますが、EXWの注意点について確認していきます。
まずは、よく使われるFOB・CIF・EXW の3つを簡単に解説します。
FOB(Free On Board)=本船渡し
•売主は港で船に積むところまでの費用・リスクを負担
•船に積んだ後から目的地までの運賃・保険・リスクは買主が負担
CIF(Cost, Insurance and Freight)=運賃・保険料込み
•売主が到着港までの運賃+保険まで負担
•買主は到着後の通関・関税・国内輸送を負担。
EXW(Ex Works)=工場渡し
•売主は自分の工場や倉庫で商品を渡すだけ
•買主は引取りから輸出通関、船賃、保険、輸入通関、国内輸送まですべて負担
→つまり、売主の負担は工場や倉庫で引き渡すまでで、そこから先は全部買主の負担となります。
EXWは、基本的に、商品の引渡しが売主の工場や倉庫であることから、税関への輸出申告書手続きを買主の名義で行います。そのため、売主側は課税売上、買主側が輸出免税の適用を受けることになります。
EXWを使用して売主が輸出免税の適用を受けるときには、売主が輸出者となり通関手続きを行うことに加え、売主から買主への商品の所有権移転の時期が輸出許可後(船積み時後)とする旨を別途契約書や覚書で明記しておく必要があります。

3.3国間貿易の場合
3国間貿易は、文字通り3つの国の間で行われる取引です。
商品が日本国内に搬入されることなく、国外で調達した商品を直接販売先へ納品する取引です。この場合、国外で商品の受け渡しが行われるため、譲渡時の資産の所在場所が国外となり、輸出免税ではなく、国外取引となります。取引3社が全て内国法人であっても、結論は同じです。商品が国内ではなく、国外で譲渡されれば、国外取引であることに変わりはありません。
ちなみに、同じ3国間貿易でも、国外で調達した商品を一度保税地域に陸上げし、通関手続きを行う前に再度国外の取引先へ販売する場合には、関税法75条の「外国貨物の積み戻し」の規定により、内国貨物を輸出する場合の手続き規定が準用され、輸出免税が適用されます。
4.郵便で輸出する場合
小包郵便、EMS郵便などの郵便物として輸出する場合、
郵便物の価額が20万円超であるか、20万円以下であるかによって、輸出取引であることを証明する書類が異なります。
⑴20万円超の場合
輸出許可書
⑵20万円以下の場合
・小包郵便、EMS郵便
「引受証」及び「発送伝票等の控え」
・通常郵便
「発送伝票等の控え」
20万円超であるか否かの判定が重要となりますが、その判定は原則として郵便物1個当たりの価額によります。
郵便物の価額とは、輸出する物品の販売金額等の実際の取引金額をいいます。
なお、郵便物を同一受取人に同一日に2個以上に分けて差し出す場合には、それらの郵便物の合計額によりますので、注意が必要です。
輸出免税に基づく還付申告については、不正還付を防止するためにも税務当局も慎重な対応をとっていますので、取引内容や必要な書類を十分確認するように心がける必要があります。
あすか税理士法人
【スタッフ】渋谷優果